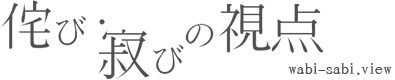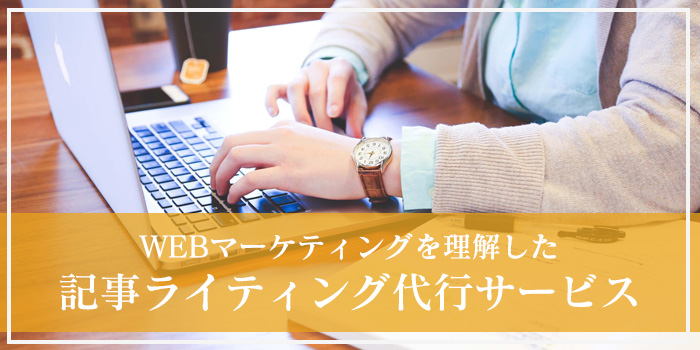多くの神社やお寺では、「懸け釜」といって、茶席が設けられます。
例えば神戸では、湊川神社、生田神社、弓弦羽神社でも、1年に何回か茶席が設けられます。
茶席は、そのときにより、流派がさまざまです。
自分が習っているのとちがう流派のお席だった場合、作法や振る舞いはどうすればいいでしょうか。
わたしは表千家ですが、裏千家のお席であっても、表の作法でお茶をいただき、またお道具を拝見します。
ほとんどの方が、ご自身の流派の作法で、お席に座られていると思います。
流派がちがっても、一服のお茶を美味しくいただく茶の湯の心は、みな共通するものですね。

ちなみに流派は、代表的なもので、裏千家、表千家、武者小路千家、藪内流、遠州流、宋徧流、有楽流などがあり、他にも多数あるそうです。
(うらせんけ、おもてせんけ、むしゃのこうじせんけ、やぶのうちりゅう、えんしゅうりゅう、そうへんりゅう、うらくりゅう)
ちがう流派のお茶席は、点前もちがいますが、お道具の雰囲気などもどことなくちがっているように感じられ、それもまた楽しいものですね。
ちがう分、学びも多いので、流派がちがうから・・とためらわずに、ぜひお席に入られてみてください。
神社のような清々しい場所の茶室でいただく、和菓子と一服のお茶を、お楽しみくださいね♪
Copyright © 2018 侘び・寂びの視点|wabi-sabi.view All Rights Reserved.